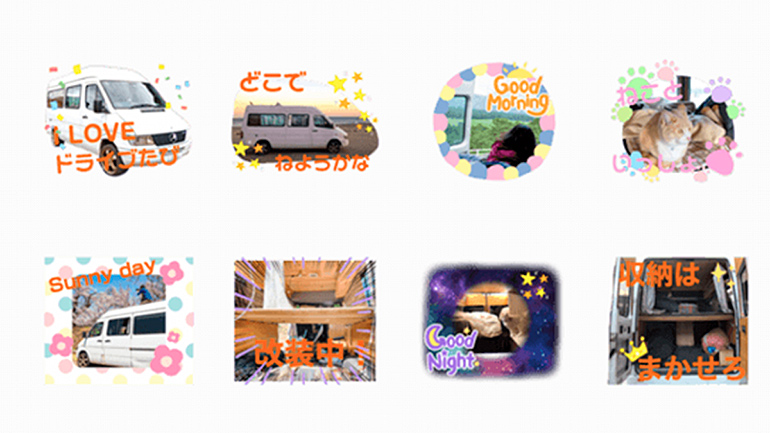看護師キャンピングカーオーナーおすすめ!!『冬の車中泊やアウトドア』に潜む危険な怪我や病気の予防策やアイテム、対処法を一挙にご紹介!

冬の時期の車中泊は積雪による絶景やウィンターレジャーを楽しめるとともに、寒い中で食べる食事や温泉巡りも格別です。
しかし事前の知識や準備が不十分な中、軽い気持ちで出かけてしまうと、寒くて寝られないどころか命の危険性も危ぶまれてしまいます。
そこで今回は、冬の車中泊に潜む危険な怪我や病気の予防策やオススメしたいアイテムをご紹介していきます。
万が一病気や怪我を起こしてしまった際の対処法も一挙にご紹介していきますので、今年の冬車中泊をしようと考えている方はぜひ参考にしてみてくださいね。
低体温症

症状
低体温症とは直腸など体の深部の体温が35度以下になることを指し、低体温が進むと最悪凍死する危険性も非常に高い病気です。
実際、近年では毎年1000人以上もの方が凍死で亡くなられており、その数は夏場の熱中症死亡件数より上回っています。
そして登山などの極寒の地で発症するイメージのある低体温症ですが、実はその約75%は屋内で発症しています。
そのため「この程度の寒さなら大丈夫」と安易に考えずに、下記の症状が出たらすぐに対処し、車中泊をする際は事前の準備と予防に心がけましょう。
・歯がガタガタ鳴り、全身が小刻みに震える
・手足の動きが鈍い
・皮膚の感覚が鈍い
・歩行困難
・うまく喋れなくなる
・呼吸が浅く速くなる etc
低体温症の予防法は?
普段は普通に生活している人でも下記のような状態にある人は特に低体温症を引き起こしやすくなります。
・過度のストレスや疲労が蓄積した状態
・慢性的な寝不足
・ダイエットなどによる極度の体重減
・運動不足による筋肉の減少
・加齢
・甲状腺ホルモンの減少
・水分不足など
特に車中泊で起こりやすい『ストレス』や『睡眠不足』は自律神経を乱し、体温調節機能を鈍くさせてしまいます。
また冬場は暖かい時期に比べると身体を動かす機会が減る方が多く、寒さに対応するための筋肉量も減ってしまいます。
そのため、普段から疲れを感じやすい方や体力が衰えていると実感する方などは車中泊をする前から『十分な栄養』と『休息』『体力づくり』を心がけましょう。
また普段は健康な方でも、車中泊は身体が冷えないような対策を取り、車中泊中もバランスの良い食事と睡眠の取れやすい環境作りを行い、脱水の原因となる飲酒のしすぎにも気を付けてくださいね。
低体温症を予防するおすすめのアイテム
低体温症を予防するためには『身体が冷えない』ことが重要なポイント。
ここでは体を冷やさないためのおすすめしたいアイテムをご紹介します。
①吸汗速乾性の高い高機能肌着
冬場の車中泊中でもスポーツなどで身体を動かしたり、暖かい車内で長時間いると汗をかくケースも少なくありません。
汗によって濡れた体はより低体温症を引き起こす原因となるため、こまめに着替える必要がありますが、冬場はよっぽどの汗をかかない限り着替えようと思う方は少ないかと思います。
そこで大切になるのが直接肌に触れる下着選び。
登山家にも愛用される「ミレーの”ドライナミック™ メッシュ」など、かさ高のメッシュ生地を使用した高機能肌着は吸汗速乾性に優れ、汗による体温低下を防いでくれます。
肌の弱い方や普段汗もかきにくいような女性の方は肌荒れしにくく一年中着用できるシルク製の肌着もおすすめです!
②吸水性・速乾性・保温性に優れたインナー
肌着の上に重ね着するインナーとしてオススメなのが吸水性・速乾性・保温性に優れたインナー。
素材としては吸水性・速乾性に優れている「ポリエステル」や汗などの水分を含んだ状態でも保温性をキープできる「メリノウール」が最適です。
『アイスブレーカーのカットソー 200 オアシス』は値段が高いのが難点ですが使い心地抜群のメリノウール100%素材でできており、耐久性にも優れているので1枚あれば長く愛用できます。
もし値段を抑えたコスパの良いインナーを手に入れたい方は、ワークマンのメリノウール100%のインナーがおすすめ。
値段は驚愕の2000円以下とコスパ最強!
しかし店頭にならぶとすぐに完売してしまうほどの人気商品のため、事前に在庫確認をしてからお店に行くことをお勧めします。
③ウィンタースポーツを楽しむならスキーウエア、焚き火を楽しむなら難燃ウエア
車旅の際にウィンタースポーツを楽しみたい方は、スキーウエアをそのまま活用とコスパも抑えられて便利です。
しかし焚き火をすると穴が空きやすくなるので、もし車中泊中にキャンプ場などで焚き火をする場合は難燃性の優れたウエアやブランケットを持って行くのがオススメです。
④保温アイテム

FFヒーターの設備があるキャンピングカーであれば車内の冷えを抑えられますが、もし普通のバンなどで車中泊をしようと考えている方は下記のアイテムもおすすめですので、用途に合わせて参考にしてみてください。
・ホッカイロ
・湯たんぽ
・ポータブル電源
・ポータブルヒーター
・ポータブルホットカーペット
・ポータブル電気毛布
・冬用シュラフまたは羽布団
・冬用敷きパッド
・コンパクト収納可能なダウンブランケット
・ポータブルヒーター搭載のベスト
・防寒手袋
・冬用帽子
・ネックウォーマー
・レッグウォーマー
・高断熱のマルチシェードなど
もし低体温症かな?と感じたら
万が一低体温症になった場合、『早期発見』と『早いうちからの対処』が重要です。
特に低体温症が重度であればあるど、急激に体温を上げようとすると最悪の場合死に至る「復温ショック」のリスクが高まります。
そのため、歯や身体がガタガタ震えるほど寒い時は温かい飲み物を飲んだりカイロや湯たんぽで首下や脇下などを温めるなどしてすぐに保温対策をとりましょう。
万が一の呂律が回らなくなったり一人で歩くのも困難になった場合は、できるだけ緩やかに温めて、すぐに病院を受診させたり救急要請を行いましょう。
凍傷

症状
低体温症と同じく、気温が0℃以下の環境に長時間いることで凍傷にかかりやすくなります。
凍傷というとあまり聞き慣れないかもしれませんが、俗に言う「しもやけ」の状態です。
凍傷になりやすい部位としては、手足の指や耳や鼻、顔。
症状としては細い針で刺されているかのような痛みや刺激から始まり、手に赤みが生じます。
その後はじんじんとした痛みや痺れが現れ、進行すると皮膚の感覚もなくなります。
凍傷になりやすいのはこんな人!
凍傷のリスクが高い以下のような方は特に注意して予防対策に心がけましょう。
・心臓や皮膚病、糖尿病の持病がある方
・普段汗をかきやすい人
・体格の小さな方や子供
・皮下脂肪の少ない方や高齢者
・喫煙者
・防寒対策を怠った方
・靴のサイズが合ってない
凍傷の予防対策は?
凍傷を予防するためには防寒と防風対策が大切です。
低体温症と同じく身体が冷えないような工夫や対策を行って血行を良くし、できるだけ頬や鼻、耳などもマスクやネックウォーマー、耳当てをするなどしてを外気に触れないようにすることも大切です。
万が一凍傷かな?と思ったら
凍傷は、寒さにさらされている時間が長ければ長いほど重症化し、回復も難しいのが難点です。
最悪のケースの場合は筋肉や骨にまで症状が及び壊疽や壊死を起こし、患部の切断を余儀なくされることもあります。
もし皮膚がピリピリしたり、赤くなるなど「凍傷かな?」と思ったら以下の方法を試してみてください。
・素早く患部を40〜43℃程度のぬるま湯に浸ける
・温かい飲み物を飲む
・患部を冷気にさらさないように保温する
・水気はしっかり拭き取る
・汗をかいてる場合は暖かい環境で着替えるなど
もし中途半端に処置をしてしまえば、患部が再凍結して症状が悪化する可能性がありますので、皮膚の赤みがなくなり、柔らかくなるまでは一定時間継続して行うことが大切です。
そして凍傷になった場合は以下のような対策は逆効果になるので、注意しましょう!
・熱い湯やストーブなどで急激に患部を温める
・患部をマッサージしたり、さすったり叩くなどして刺激する
・水ぶくれを破く
一酸化炭素中毒

症状
車中泊の際に特に注意してほしいのが一酸化炭素中毒です。
症状としては頭痛やめまい、嘔吐、意識障害などの症状を引き起こし、最悪の場合は死に至るリスクも高まる病気です。
実際、車中泊中に一酸化炭素中毒を引き起こし亡くなられたケースもあるため、冬に車中泊をする方は特に注意をしましょう。
一酸化炭素中毒を予防するためには?
車中泊中に一酸化炭素中毒を起こさないためには以下の点に注意しましょう。
・密閉空間の車内で火気を使用しない
・換気を定期的に行う
・エンジンはつけっぱなしにしない
・エンジンをつける前にマフラーに積雪が埋まっていないか確認する
おすすめのアイテム
一酸化炭素中毒を予防に便利なアイテムは『一酸化炭素警報機』です。
車内の一酸化炭素の濃度を感知し、アラームで危険を知らせてくれますが、電池切れや故障する可能性もあるので、できればメーカーの異なったものを2種類用意しておくことをお勧めします。
一酸化炭素中毒かな?と思ったその時は

万が一エンジンをつけた車内で過ごし、頭痛や吐き気、めまい、不快感などの症状が現れた際は落ち着いてエンジンを止め、換気を良くしましょう。
もしも症状が改善しない場合や意識障害が現れている場合は車の運転は避け、すぐに救急要請を行い病院を受診しましょう。
次のページ⇨ 他にも起こり得る危険な病気を3つ紹介します!
ヒートショック

ヒートショックとは?
ヒートショックは、暖かい環境から急に寒い場所に移動したり、寒い場所から暖かい場所に移動するなど、急激な温度の変化に伴って起こる健康被害のこと。
急激な気温差は身体の血流の変動に影響を及ぼすので、最悪の場合、心筋梗塞や脳梗塞、脳出血などの恐ろしい病気を引き起こします。
どんな人が起こしやすい?
ヒートショックを起こしやすい方は以下のような方です。
これに該当する方は特に注意して予防対策を行いましょう。
・65歳以上の方
・高血圧・糖尿病・動脈硬化・不整脈などの基礎疾患がある方
・肥満の方
・睡眠時無呼吸症候群がある方
・キャンピングカーの車内にトイレがなく、車内と外を行き来する機会が多い方
・冬場に温泉巡りを楽しむ方
・食事や飲酒後に入浴する方
・熱い湯温を好む方
・入浴の時間が長い方
冬のアウトドアや車中泊でヒートショックを予防するためには?

温度差が生じやすい冬のアウトドアや車中泊中は以下のことに注意して予防するようにしましょう。
・外に出る時は帽子・マフラー・手袋などを装着し防寒着を必ず着用する
・外に出るときは家族に一声掛け、万が一に備えて携帯や防犯ブザーを携帯しておく
・排便時は無理にいきまない
・食後や飲酒、服薬後の入浴は避ける
・入浴前後は必ず水分補給する
・身体を徐々に温めてから41度以下の湯船に浸かり、長風呂は避ける
・湯船から出るときはゆっくり立ち上がる
・お風呂上がりはしっかり水分を拭き取り、髪の毛も乾かし、脱衣所や室内でゆっくり身体を冷ましてから外に出る
もしもヒートショックかな?と思ったら
急激な温度差の後にめまいや立ちくらみを生じた際は軽度のヒートショックを起こしている可能性があります。
その際は無理に動こうとはせず、安静にして症状が治るのを待ちましょう。
万が一呼吸困難や嘔吐、意識障害、急な胸の痛み等の症状があれば速やかに他者に知らせたり、救急要請を行いましょう。
万が一入浴中にヒートショックになった人を見つけた場合は、ご本人が湯船から出るのを手伝ったり、溺れないように湯船の水を抜いたり、顔を水面から出すようにしてあげ、大声を出して他者に救急要請を依頼するようにしましょう。
低温やけど

低温やけどとは?
保温対策としてして手軽に活用しやすいカイロや湯たんぽ、ポータブルヒーターやホットカーペット、電気毛布で注意して欲しいのが『低温やけど』です。
低温やけどは普通の火傷とは異なり皮膚の奥深くでゆっくり進行するので、症状に気づきにくく、気づいた時には重症化していたケースも少なくありません。
どんな人がなりやすい?
低温やけどは以下のような方がなりやすく、特に気温が寒く感覚が鈍くなる冬の時期には注意が必要です。
・皮膚の薄い高齢者や子供
・寝返りができない乳児
・心臓病や皮膚病、糖尿病などで手足の循環が悪い方
・飲酒しすぎた方
・体温が下がり体の感覚が鈍くなっている方
低温やけどの予防対策
発症に気づきにくい低温やけどは事前の予防対策が大切です。
上記に当てはまる方以外でも注意が必要なので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
・泥酔するほどの飲酒は避ける
・ポータブルの電気毛布やヒーター、カーペットはタイマーを設定しておき、寝る前には消す
・感覚が鈍くならないよう防寒着を着用しておく
・カイロや湯たんぽを直接皮膚にあてない
・一ヵ所に長時間カイロを当てない
・少しでも熱いと感じたときはすぐにカイロや湯たんぽをはずし、電気暖房器具を切る
・就寝時には使用しない
万が一低温やけどになったら?
万が一患部が赤くなったり、痛くなれば速やかに清潔な流水ですぐに冷やしてあげましょう。
衣服を無理に脱がす必要はありませんが、低体温症を予防するために必ず暖かい場所で20分ほどを目安に冷やしてあげましょう。
万が一水泡や水ぶくれができた場合は、破れるとそこから雑菌が入り感染症を起こす可能性があるので、無理に破かないようにしましょう。
また、低温やけどは早めの対処が必要ですので、自己判断をせず、病院を受診することをお勧めします。
脱水症状

冬なのに脱水?!
冬の時期にはイメージしにくい脱水症状ですが、夏に比べると意識的に水分を摂ろうとする人が少ない分、脱水症状になる方も少なくありません。
特に冬の時期は空気が乾燥することで、いつの間にか体内の水分が奪われ、汗をかいている自覚も少なく、喉の渇きを感じにくいのも要因とされています。
冬も夏同様に脱水症状に気をつけよう

寒い時期に飲みたくなるコーヒーやお茶、ホットワインや熱燗などのアルコールは利尿作用によって脱水を助長させます。
そのため、飲み過ぎには注意し飲酒した分以上に白湯などの水分を適宜飲んだり、バランスの良い食事摂取を心がけるなどの工夫を行うことが大切です。
また車内の乾燥を予防するためにポータブル加湿器を使用するのもおすすめですよ。
事前準備万端で冬のアウトドアや車中泊を楽しもう!
今回は冬のアウトドアや車中泊で特に注意してほしい病気や怪我をご紹介しました。
読んでいくと怖くなる方もいるかもしれませんが、きちんとした知識を予防対策を行うことで冬も車中泊やアウトドアを楽しむことができます。
しかし油断は大敵ですので、万が一想像以上の極寒環境や体調が優れない場合は途中で中断する勇気を持つことも大切です!
今回の記事はアウトドアだけでなく日常生活でも活用できる内容ですので、ぜひ参考にして今年の冬を過ごして下さいね。